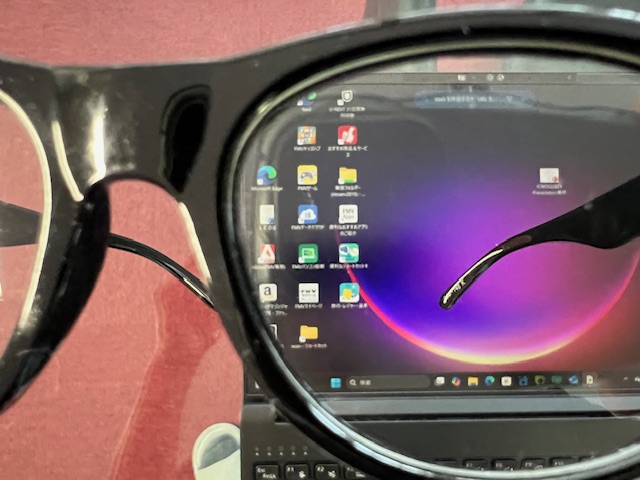Chapter 219
自動車関税は15%に落ち着いて最悪の事態は免れたが、地政学リスクが高まって世界経済の不確実性が高まった。これは共和党トランプ政権が原因ということではなく民主党バイデン政権を含む過去の負の遺産と言うべきかもしれない。物事には両面あるので良し悪しではない。1980年頃のハリウッド映画を見るとニューヨーク中心部の荒廃ぶりが描かれていて、現代の若者には想像もつかないアメリカの姿が思い出される。マンハッタンの高層ビル街にホームレスが溢れ、地下鉄の車両や駅は落書きだらけで犯罪率が高かった。社会学者エズラ・ボーゲル著Japan as Number One:Lesson for America(1979)は日本を最高に持ち上げた著作だが、当時の富の象徴ロックフェラーセンターやハリウッドの映画制作会社コロンビア・ピクチャーズをSONYが買収したほか、タイムズスクエアの電飾看板は日本企業の広告で埋め尽くされた。ビルや企業を買いまくる日本が今の中国のように悪者扱いされるのは当然であり、叩かれたのは日本半導体だけではない。デトロイトの労働者によって日本車が叩き潰されて焼かれる映像は未だに脳裏に焼き付いている。家電その他、すべての日本製品が標的になった。著者は社会学者なので、日本人の優れた特性、学ぶ力の高さを称賛し、米国人も見習って学ぶべきだと警鐘を鳴らした。記述では、日本人の数学力や科学力が世界2位。読書時間は米国人の2倍で学習意欲が高く、経済産業省や大蔵省の強烈な関与が競争力を高めているとした。その後のバブル崩壊は、米国の日本叩きに沿った内容で、国策として国民を骨抜きにするリゾート法によって飲めや歌えやの狂乱に突っ走ったのはご承知の通りである。教育現場でも受験地獄を改めて余裕が強調された。従って、国力衰退は国の失政というより時代の流れで避けられないことだった。但し、半導体は失われた30年になったが、自動車産業は世界No.1の地位に返り咲いた。この差は何か?半導体は投資リスクが大きいビジネスで国策に依存する部分が大きい。IBM等、米国が優位だったのを、経済産業省のお膳立てで日本電気(NEC)、富士通といった官製企業(日本電信電話公社NTTが発注する電気・電子製品の受け皿)が中心となって研究開発と設備投資を行うことで一人前に成長したものの、苦労知らずのボンクラ息子はちょっとした挫折で立ち直れない。一方の自動車産業は、自動車好きで欧米の車に憧れて情熱を持って追い着け追い越せで切磋琢磨した苦労人だから逆境に強い。形勢が悪くなっても現地生産を進めるなど、自ら必死に生き残り策を考えた。しかし、それも「出過ぎる杭は打たれる」結果になった。90年代後半に情報化時代を先取りしてITベンチャーが米国経済を救ったが、そのITベンチャーの成長に陰りが見え始めて、今まで気にもかけなかった自動車産業がまた気になり始めて保護主義に走らざるを得なくなったというところか。トランプ大統領に媚びるように献金するGAFAmの姿は且つての強気なヤンエグとは別人で小さく見える。頼みのAIにしても、知れば知るほど、ただの進化した検索ソフトと思える。今後の成長を期待する気持ちを込めてAIと呼ぶのかもしれないが知能と呼ぶのはおこがましい。ハード面でARグラスといった新たなマン・マシン インターフェースの登場が期待される。
令和7年8月4日
先の見えない世界情勢